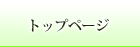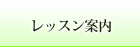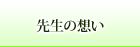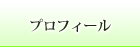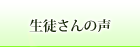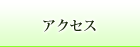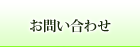客観的な視点を持って学習する
水曜日は幼稚園の年長さんが前後で2人、お稽古に通ってくれています。
先にレッスンが始まるのはEちゃん。「ハタ上げゲーム」の5本にチャレンジ中ですが、ついに今日、念願のノーミスで取る事が出来ました。
Eちゃん曰く「青色と黒色が間違いやすいから、その2本を気を付けて聴いた」との事。
幼稚園児にして彼女はとても素晴らしい事に気が付いています。
それは「自分が何を得意とし、何を苦手としてるか把握できている」という事です。
Eちゃんは「赤色や黄色のハタは結構分かるから大丈夫なんだけど、青色と黒色は音が似ているからよく聴いておかないと間違っちゃうんだよね」と自分がミスをする原因がきちんと分かっているのです。
つまり自分のミスを客観的な視点から見ているのです。
我々大人からすると「そんな事、当たり前じゃないか」と思われますが、実は幼児は自分自身の事を客観的に捉える事が難しいのです。
自分を客観視できるのは10歳以降から
以前に参加した「脳科学」のセミナーで習った事ですが、人間は10歳程度まで成長しないと「客観的」「抽象的」な物の見方が出来ないのだそうです。
個人差はありますがそれより小さい年齢ですと、ほとんどの子供が「自分が見たり聞いたりして体験した事」しか想像できないのだそうです。
ですのでもし小さい子供に「自分の良いところを挙げてごらん」と言っても、なかなか言葉が出てこないと思います。
その場合ですと「いつも元気にご挨拶ができるね」や「○○ちゃんは優しいね」と具体的に長所を挙げて、子供に「私はそういう人なんだな」と教えてあげると良いそうです。
反対に勉強などでいつも似たような問題を間違えるのに、それを本人に指摘しても今一つピンと来ていない様子で、「この子、本当に分かっているのかしら」と気を揉んだ経験のある保護者は多いかと思います。
これもまた、脳の発達に関係している可能性があります。
例えば音符がなかなか覚えられない子供が合格した曲に関してはきちんとドレミが読めるのに、新しい曲に進むと途端に読めなくなる現象も同じです。
彼らにとって先程まで弾いていた曲の中に出てくるドレミと、これから弾く曲の中のドレミは「同じである」という認識が無いのです。
楽譜の中のドレミ、音符カードに載っているドレミ、五線ノートに書くドレミは実は同じであるという発想は、少し引いた視点から見ている状態です。
小さい子供の頭の中では、一連のドレミ群は別々に存在しているのです。
これらのドレミを「実は全部同じなんだ」と合致させる為には、練習の回数をこなして定着しかありません。
Eちゃんは「私は青色と黒色の聞き分けが苦手。だから青色の音はこれ。黒色の音はこれ」と、とても注意深く聴いて、2つの音の微細な違いを判断し、耳に覚えさせようとしているのだと思います。
そうやって自分自身の得手・不得手を少しずつ把握し、それを克服する為には具体的に何をどう工夫すれば良いのか考え、またサポートしてあげると同じ思考パターンをピアノだけでなく勉強の面等にも応用することが出来ると思います。
関連記事
-

-
連弾合同レッスン 大人編その1
学生さん達は冬休みに突入しましたが、今回の休みは連休が最初と最後にあるので例年よ …
-

-
連弾合同レッスン その1
1月中旬より子供の生徒さん達も連弾合同レッスンを始めています。 今週はその2回目 …
-

-
2018年度 連弾合同レッスン その2
今日の連弾合同レッスンは小学6年生のAちゃんと5年生のAちゃんの「AA」ペアです …
-

-
2018年度 連弾合同レッスン その14
本日ご紹介する連弾ペアは小学2年生同士のEちゃんとSちゃんです。 2人共とても真 …
-

-
ごほうびグッズ ゲット達成!
ついに最初の「サマーチャレンジ」中間結果で、ご褒美グッズをゲットした生徒さんが現 …
-

-
ドレミは日本語?
私の教室ではピアノを習い始めて日が浅い生徒さんは、発表会に参加しません。 人前に …
-

-
初めての「ダルクローズ・リトミック」体験! その1
11月も末になり朝夕が冷え込み始め、ようやく秋らしい季節となってきました。 今日 …
-

-
2017年 連弾合同レッスン その1
2017年の発表会に向けての連弾合同レッスンは、実は大人の生徒さんペアはもう始ま …
-

-
中級にレベルアップしました。
土曜日の午前中はAちゃんのレッスンがあります。 今日は「スケールテスト」の再試験 …
-

-
明日から12月
1週間秋休みを頂き、その間に事務処理、教室だよりの作成、新年度の開講日程、アンサ …
- PREV
- 音楽教室の役割
- NEXT
- 主体性を持って学習する