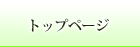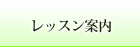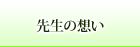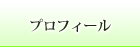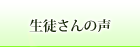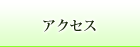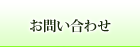ドレミは日本語?
私の教室ではピアノを習い始めて日が浅い生徒さんは、発表会に参加しません。
人前における演奏は、やはり半年以上の習っている経験が無いと、本人も自信をもって弾くのは難しいだろうと考えているからです。
偶然ですが本日火曜日は、今年に入ってピアノを始めた生徒さんが何人か在籍しています。
どの生徒さんもお家での練習のやり方やペースの掴み方を学習し始めた段階です。
そんな本日最後のレッスンは、木曜日に小学校の卒業式を控えた小学6年生のNちゃんです。
「セカイノオワリ」などJポップが好きなNちゃんのために、レッスンでは「コードネーム」についても少し触れています。
ギターでもおなじみの「Gメジャー」「Cマイナー」等のコードネームは、ご覧の通りアルファベットの「ABC」を使って表記します。
では音楽の教科書にも使われている「ドレミ」と言う呼び方は日本語なのでしょうか?
ドレミという呼び方はイタリア語
小学校で習う「日本語の中でも、外来語はカタカナで表記する」原則に基づいて考えると、「ドレミ」は日本語でない事が分かります。
実は「ドレミファソラシド」はイタリア語の言い方なのです。
9世紀から10世紀にかけてイタリアのキリスト教会の中で発展した「グレゴリオ聖歌」の中の1曲、「聖ヨハネ賛歌」の冒頭の歌詞がちょうど音階の各音にあてはまっていたので、「分かりやすい」と修道院内で使われるようになり、やがてヨーロッパ各国へと広まって行きました。
元々、歌から採用された呼び方なので言いやすいのが特徴で、現在でも世界中のどの国も歌は「ドレミ・・・」で歌われています。
それに対し、ドイツ語圏や英語圏の人々は器楽のための呼び方としてアルファベットそのものの「ABC」を用いました。
「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」をアルファベットに置き換えると「C・D・E・F・G・A・B(ドイツ語ではH)・C」となります。
ポピュラー音楽に出てくるコードネームが英語表記なのは、ポピュラー音楽の発祥地がアメリカやイギリスであった為です。
ちなみに義務教育課程でも習う「ハ長調」や「ト長調」と言った呼び方は日本語での「ドレミ」の呼び方です。
「ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・イ・ロ・ハ」、これが日本語におけるドレミの呼び方なのです。
日本の音楽教育では以上の3つ(イタリア語・英語・日本語)の呼び方が混在し、しかもそれを同時進行で教えられるので、学習者にとってややこしい事態を招く結果になりました。
最後に「ドレミ」に対し、なぜ英語や日本語の呼び方は「CDE~」や「ハニホ~」といった途中の文字から始まるのかについてですが、これは中世の音楽理論家であったボエティウスが西暦500年頃に著した書物「音楽教程」に由来しています。
彼はその中で全音階の各音にアルファベットを付したのですが、その際に音階を今で言う「ラ」の音から記した為に、この音が起点になりました。
なので「ラ」に当たる音に始まりの文字である「A」や「イ」が当てられており、それが21世紀になった今でも使われているのです。
関連記事
-

-
連弾合同レッスン その1
1月中旬より子供の生徒さん達も連弾合同レッスンを始めています。 今週はその2回目 …
-

-
調号の付け忘れを無くす為には
夏休みも残り1週間程度になってきました。 今日も「ごほうびグッズ ゲット達成!」 …
-

-
2018年度 連弾合同レッスン その16
今週末にあたる3月23日(土)に、2018年度の発表会を石井町中央公民館「藤ホー …
-

-
ピアノを弾く時の姿勢 その2
床に足が届くようになってからも注意が必要 床に足が届く年齢になっても、正しい姿勢 …
-

-
指番号を一致させる
今日は11月から習いに来てくれているEちゃんのレッスンでした。 とても元気な明る …
-

-
2018年度 連弾合同レッスン その12
さてご紹介している連弾ペアも残り少なくなって参りました。 本日は2組のぺアをご紹 …
-

-
新しい生徒さんのレッスン その1
今日は12月から当教室に通い始めてくれた年中さん、Rちゃんのレッスンでした。 レ …
-

-
リトミックレッスン2019 その2
7月7日の七夕の日に行われた、第2回目のリトミックレッスンです。 今回のテーマは …
-

-
連弾合同レッスン 大人編その2
年内の通常のレッスンは28日で終了し、今日は振替対象者の為の「補講日」です。 今 …
-

-
中級にレベルアップしました♪ その2
梅雨明けした途端に日本列島は全国的に猛暑に見舞われておりますが、こちら徳島県も例 …
- PREV
- 連弾合同レッスン その6
- NEXT
- 2016年度発表会が終了しました。